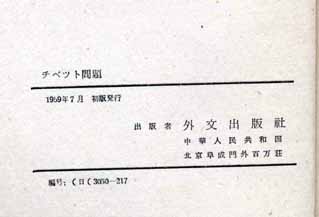

[メインページに戻る ]
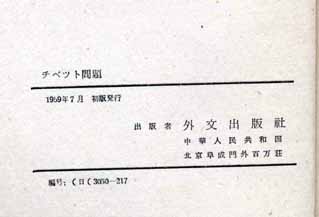

(1) 日本人の貧困なチベット観 ※注 これ1999年に書いているので、現在はずいぶん日本の状況もかわってまーす!
夏休みが近づくと学生から「チベットに行きたいのですが、チベット大使館はどこにあるのですか」などの質問を受け、脱力することがある。ご存じの通りチベットは中国に併合されチベット大使館なるものは存在しない。しかし、このような
中国にとってチベット問題は国内問題である。チベットが独立なんてことになれば、55ある他の少数民族が何を言い出すかわからないし、少数民族が居住している区域が分離すれば中国から広大な地域が失われ、あっというまに中国は混乱状態に陥ってしまう。中国が混乱すれば一衣帯水で隣接する日本にとっては、政治的・経済的にもデメリットが大きいため、日本の新聞社はあまりチベット問題をとりあげたがらない。
東アジアの政治情勢の混乱は筆者としても望むところではない。しかしそれとは別の問題として、中国がチベット問題を語るときに用いる一連の論理について、研究者の良心から一言言いたいことがある。中国は「チベットは歴史的にいって中国の不可分の一部である」と、こと有るごとに主張する。それを無責任にたれながす日本のマスコミも少なくはない。しかし、このテーゼは「歴史的にいって」まったく偽なのである。チベットが現在のように「中国の一部」となったのは、1950年の中国軍の占領に始まり、1959年のダライラマ14世のインド亡命に終わる、一連の事件の結末である。それ以前のチベットは、中国とは全くことなった言語・歴史・文化・社会を有する独立体であった
。
7世紀に統一王朝として姿を現した古代チベット王朝は、時の中国王朝唐と対等にわたりあう強力な軍事国家であった。822年に唐とチベットの両方の都に建立された碑文に「チベット、中国の両者は現在支配する領域を守って、東方すべては大中国の地に、西方すべてはまさに大チベットの地にして、これより後は互いに敵対し諍うことなく、領域を侵犯することなく、・・・チベットはチベット国において安らかに、中国は中国において安らかになさん。」とあるように、両国は当時明らかに別の政体に属していたのである
(当たり前だけど)。
(2) チベット仏教で国を傾けた元朝
それでは、中国は何をもって歴史的にチベットを不可分の一部であると主張するのであろうか。中国の主張によれば、中国は元朝と清朝の二時期にわたってチベットを「直接支配」してきたという。そこでまず、この二つの時代の中国とチベットとの関係を、中国当局の見解にも、チベット亡命政権の見解にも偏ることなく、最新の歴史学の成果をふまえて検討してみよう。
1260年、チンギス=ハーンの孫であるフビライ=ハンは、中国に元王朝をたて、その都を大都(現在の北京)に定めた。チベット仏教の一派サキャ派の座主であったパクパ(1235-1280)は、このフビライ=ハンに国師として推戴され、フビライが大都で行う王権儀礼を演出した。
最新の研究によると、フビライは自国の軍隊に降伏した国々、たとえば、高麗(現朝鮮半島) や安南 (ベトナム) に対して、駅伝の設置、元朝の宮廷に王族の子弟を人質としてさしだすこと、人口調査、軍事協力、納税などの義務を一律に課していた。実際、元朝はチベットに対して人口調査を行い、駅伝を設置している。サキャ派の座主を帝師として元朝の宮廷にとどめたことが「王族の子弟を人質にさしだした」ことにあたるとすればすべての項目は満たされ、たしかに、元朝はチベットを属国として遇していたということにもなろう。しかし、フビライ=ハンが死んでテムル=ハンが即位すると、元朝はチベット統治に関心を示さなくなり、一方、元朝の王族のチベット仏教に対する強い信仰は相変わらず持続し続けた。つまり、それ以後の元・チベット関係は、政治的主従関係よりも、純粋に宗教的な師弟関係に移行していったのである。元朝一代を通じ、元朝の王族はチベット仏教に心酔し、寺を建て、大蔵経を開版し、囚人を釈放したため、これらの一連の行為は元朝滅亡の一因ともいわれている。つまり、元朝のチベット支配は、行われたとしても非常に短期間であり、それも宗教的尊崇という外衣をまとったきわめて穏やかなものであったのである。
(3) 文殊皇帝としての清朝皇帝
次に、中国が同じくチベットを直接支配していたと主張する清朝時代について検討してみよう。中国がチベット直接支配の始まりと見る事件は1720年の清朝軍のチベット侵攻である。この1720年の軍事行動の詳細を最新の研究に基づいて見ていこう。
1717年、ジュンガル部長ツェワンラプタンが突如チベットに軍を送ってラサを占領した。彼等は清朝の後援するダライラマ六世を廃して、前六世の転生者とされる童子をダライラマ七世として即位させようとしていた。しかし、このダライラマ七世の候補者は当時青海ホショト(青海ホショトはダライラマ政権の成立にあたって軍事的後援を行ったモンゴルの一部族である)の手中にあり、青海ホショトは清朝の牽制をうけて動くことはなかった。
1720年、清朝は青海ホショト軍を説得すると、文殊菩薩皇帝としてダライラマ七世候補を擁してラサに侵攻し、同年10月には、ポタラ宮で正式にダライラマ七世として即位させた。ラサを占領した後、清朝・青海ホショトの連合軍はチベットの貴族と協力して秩序の回復にあたり、青海ホショトからチベット王を選出させようとしたが、ジュンガルを裏切って清朝に与するまでの一連の経緯の中で、青海ホショトの内部は不和の極に達しており、一致してチベット王を選出できるような状況にはなかった。清朝はダライラマ位をめぐってモンゴル内部で争いが繰り返される状況を嫌忌し始め、1723年、清朝は青海ホショトの内訌を口実に軍をおくって青海を制圧した。この事件を契機にして、青海ホショトが果たしてきたダライラマの後援者という歴史的役割は、かわって清朝のものとなったのである。清朝はチベットの秩序をモンゴルが攪乱することを防ぐため、ラサに一人の大臣を常駐させてチベットでおきる出来事を報告させた。これが駐蔵大臣のおこりである。
以上の1720年前後のチベット・清関係を見ると、清朝は自らが認定したダライラマ六世を自らで否定しチベット人の支持のあるダライラマ七世を擁せざるをえなかったこと、文殊菩薩皇帝を自称していたこと、青海ホショトから王を選ぼうとしていたことなどから、つねにチベット側の論理にふりまわされていたことが分かる。また、1720年以後も清朝はチベットの社会に変革を加えた事実はない。1723年に雍正帝が即位すると、ジュンガル防衛のために残留していた清朝軍もチベットから撤退した。この出来事に限らず、清朝の西北方面(中央アジア・モンゴル・チベット)への出兵は、秩序回復を目的にやむなく行った場合が多く、事がおさまった後にも、現地社会に対して根本的変革を加えた例はほとんどない。乾隆帝の「俗によりて以って治む」という言葉が表しているように、清朝の対民族政策はその民族の習俗に従うことが原則であった。大臣を現地に駐在させたような場合でも、その人物には、単に現地の事情をモニタリングしたり、清朝の立場を現地に伝えたりする大使のような役目を行っていたのである。その後、清朝皇帝はチベット仏教の保護育成に心をくだき、チベット文化はチベット・モンゴル・満州という強大な教圏をえて富み栄えたのである。
(3) 中華思想の恐怖
以上、元朝・清朝の二例を検討すれば明らかなように、中国がチベットを直接支配したと主張する時代には、多くの共通点が見られる。両方とも漢民族の王朝ではないし(元朝はモンゴル人、清朝は満州人)、また、両王朝の支配によってチベット社会が変革を加えられたということはなく、むしろその後援によってチベット文化が富み栄えていたという点である。
この二王朝と現在の中国のチベット支配を比べてみれば、その差は一目瞭然である。1950年以後、漢民族がチベットに対して行ってきた民族固有の文化の組織的破壊、王様が乞食にものをなげあたえるような経済援助は、過去二王朝の時代のチベット・中国関係では決して行われたことのなかったタイプの政策である。この違いは現代中国が漢民族によって運営されていることとは無縁でないだろう。漢民族は儒教文化のもとで中華思想という歴史理論を育んできた。中華思想とは、天下にはただ一つ中国という国しかなく、文明は中国文明しかないと考え、周辺の未開の諸国はいずれ文明化して中国と同化するか、野蛮なまま中国文化の侮蔑の対象となるしかないという偏狭な大国思想である。この論理のもとでは、文明の多様性は認められず、主権をもった複数の国家が存在する国際社会などは許容されない。この思想は、成立した当初の春秋戦国時代ならいざ知らず、西洋文明の存在があり、かつ、東アジアにいくつもの文明が生まれ育っている現在、とうてい有効であるはずもない。しかし、残念ながら現代中国がチベット問題について語る際に持ち出してくる歴史的認識は、明らかにこの中華思想の影響を受けている。「チベットは歴史的に言って中国の不可分の一部である」という主張は、彼らの中華思想に基づけば真なのである。
しかし、もし、中国がチベット問題を平和裏に解決したいのであれば、国際的に通用しない中華思想をふりかざすよりも、まず、過去の皇帝達の行いにならってチベット文化に対する理解と、相手に対する尊重の気持ちをもち、その上で誠実にチベットと向き合うことであろう。実は、現代中国は1980年代後半より、わりとそのような路線をとりはじめているのですが、それについてはまた今度
(今度はあるのか?)。(1999年筆)